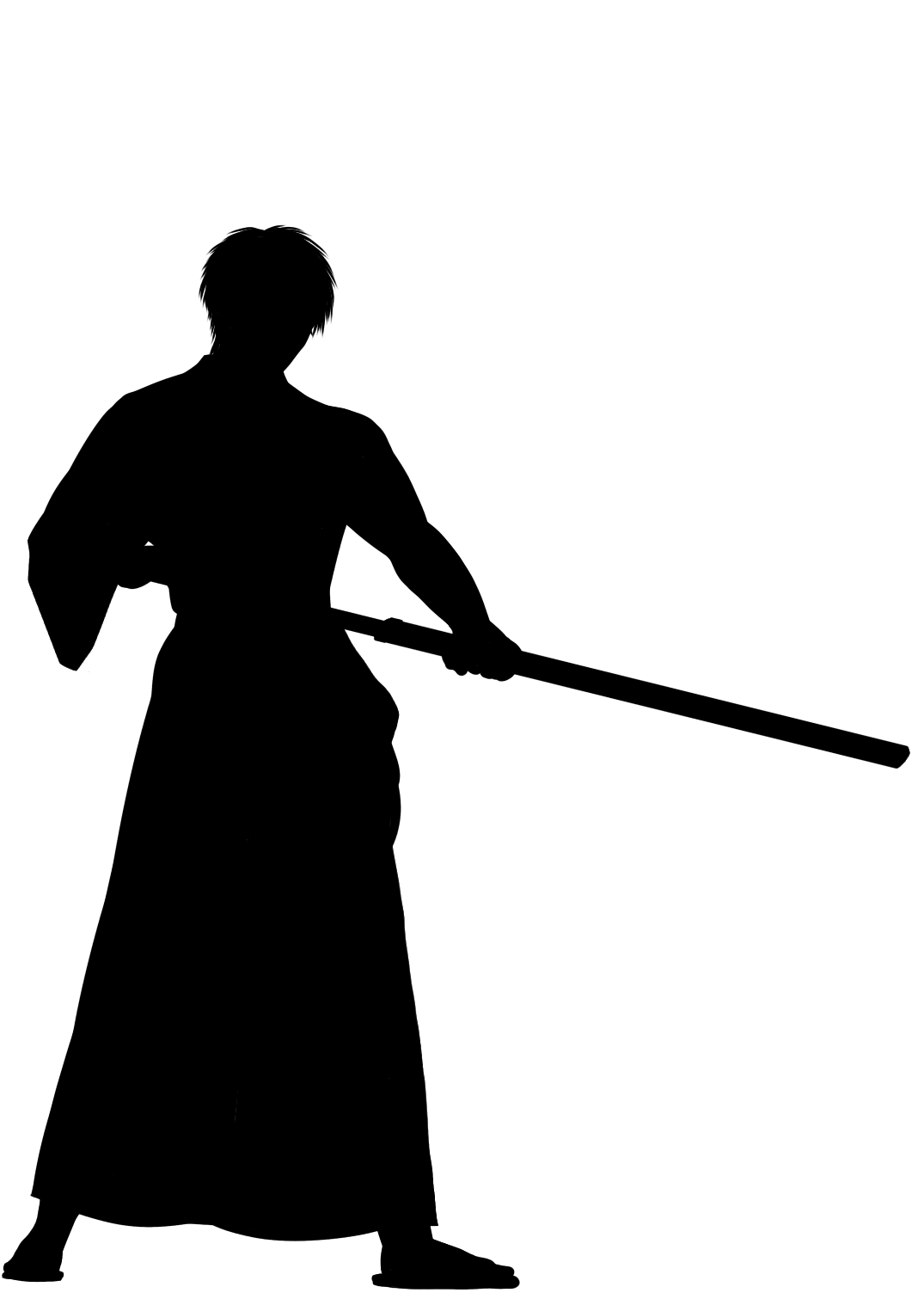日本の武士は単なる兵士ではなく、「伊達」と「粋」とに己のアイデンティティを絡める若者でもありました。「傾奇者」とは奇を衒った格好をして目立つことで大名に取り入ろうとする者を指したのですが、兵士としての自己実現を果たすことの難しかった江戸時代では、自己表現欲求の現れでもあったのです。ファッションにもその兆しが見られ、わざと重ね着をして派手に見せたり、大きな刀を差したりしました。刀に寄りかかって一丁前のポーズを決めるナルシストまでいました。そこでは日本刀もファッションアイテムの一つだったのです。
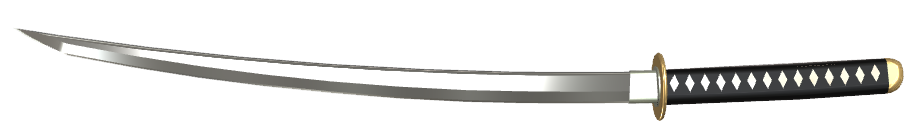
では戦国時代はどうだったのでしょうか。殺し合いの現場は正に阿鼻叫喚の光景であったことは想像に難くありません。しかし刀の取り扱いは冷静に正しく行わなければなりませんでした。刀を鞘から抜いた「抜身」の状態で好き勝手に行動すると、自分や味方の身体を簡単に傷つけてしまいます。「関ケ原合戦図屏風」に見られるように、戦闘中とはいえ、冷静な扱いが命じられていました。抜身を横たえることは禁物でしたし、利き腕で長く持ち運ぶことも禁じられていました。刀にはそうした厳格な行動を強いるはたらきもあったのです。

「武士道と云ふは死ぬ事と見つけたり」とはあまりにも有名な一句で、山本常朝が著した「葉隠」に記されています。武士についてそれほど勉強していない現代人の先入見でもあるこの「武士道」は、確かに一部の武士の間で持て囃されました。しかし実際は武士の中にも意志の弱い者はいましたし、刀を神聖視していない武士も少なくなかったのです。現存する武士の日記として有名な「鸚鵡籠中記」や「石城日記」にも、大道芸に夢中になって刀を盗まれた為体や、料亭で無造作に刀を放り投げる武士もいたことが記されています。
おすすめの日本刀専門:日本刀や刀剣の買取なら専門店つるぎの屋